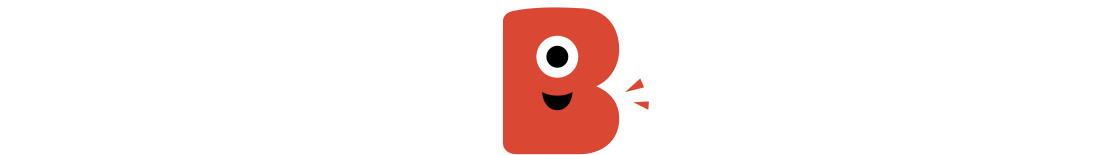Case 1
属人化が生んだトラブル連鎖
Before
特定の担当者に業務が集中し、誰も状況を把握していない。障害が起きたときも代わりが効かず、復旧の遅れが続いた。
「エスカレーションってどうすれば?」「誰に聞けばいいのかも分からない…」
── そんな声が現場にあふれ、上司や事業部からの信頼も揺らぎ始めていた。
After
「いったん、やってる業務を書き出してみよう」から始まった業務の棚卸し。
タスクの割り振りを見直し、対応マニュアルと定例の情報共有を導入。いざという時に“誰でも対応できる”体制ができ、
「チームとして回ってる安心感がある」と現場に落ち着きが戻った。