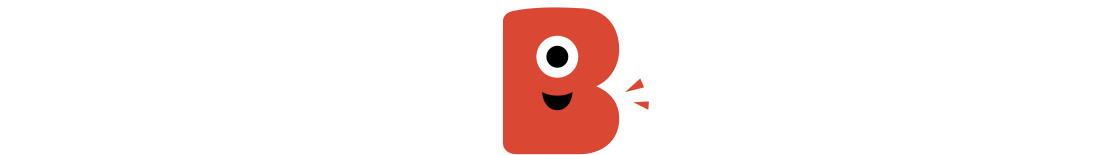「必要な保守」と「不要な保守」の線引きによる業務最適化
【実施の背景】
保守業務はシステムの安定稼働に欠かせない一方で、そのすべてが“やるべき仕事”とは限りません。 特に、将来的にリプレースが決まっているシステムや、影響範囲が限定的な障害に対しては、改善や手直しを進めることがかえって無駄や混乱を招く場合もあります。

課題
- どこまで対応すべきかの判断が現場任せになりがちで、改善活動が属人化していた
- 影響度の小さい問題にも過剰対応してしまい、かえって業務やコストの負担が増加
- 「すべき保守」と「やらなくても良い保守」の整理基準がチーム内で統一されていなかった
解決策
設計書への“ユーザー視点”の情報追記
- 稼働時間、利用頻度、業務への重要度、許容停止時間など、ユーザー視点の運用情報をドキュメントに明記
- 障害や課題が発生した際に「どれほどの対応が必要か」をチーム全体で判断可能に
総合的な優先順位の判断基準を明文化
- 影響範囲、暫定対応の可否、改善コストやリードタイムなどを軸に、対応すべきか否かを定量的・定性的に判断できる基準を策定
- 無理に“完璧な保守”を目指すのではなく、目的に沿った対応方針を共有
中長期の予防保守への切り替え
- 1〜2年先を見越して、保守切れや非推奨技術の更新計画を棚卸し
- 今すぐ対応せずとも、将来的な対策を計画化することで「今、無理にやらない判断」が可能に
【特別な取り組み】
- 保守対応の意思決定をチーム内で見える化し、「やる/やらない」の判断理由を共有
- タスクの精選により、コストや時間を本当に必要な業務に集中させる体制を構築
- 「提案する保守」「成果が見える保守」を重視し、顧客への提案力・継続支援力を向上
「保守のやりすぎ」を防ぎながら、必要なことに集中する運用スタイルへ移行することで、現場の疲弊を抑え、チームとシステム双方の健全性を高める取り組みが実現しました。今後も“正しくやらないことを選ぶ”判断力を持った運用チームを支援していきます。